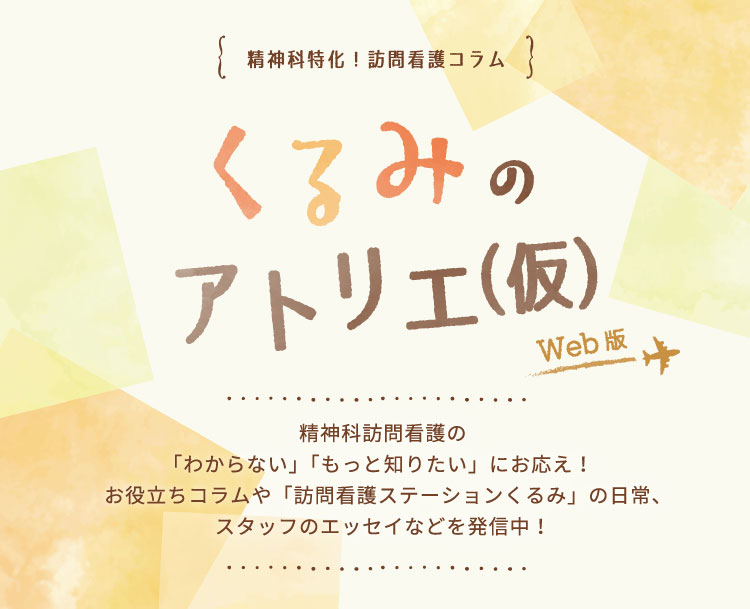看護師の中村です。このエッセイは今回で第3回になります。
僕は音楽が好きで、色々な演奏を聴きに行っています。先日、あるピアニストのコンサートに行ってきました。今回は、その演奏を通して、元通りにならない時間の中で、それでも続いていくものについて書いていきたいと思います。
大阪市、寝屋川市、守口市、
門真市、大東市、枚方市全域対象
“精神科に特化”した
訪問看護ステーション
「くるみ」
平日・土曜・祝日 9:00〜18:00
【日曜・お盆・年末年始休み】
※訪問は20時まで
対応させていただいております。
ブーニンとの出会い
小さい頃からピアノを習っていた影響もあって、小学校の高学年になると、自然とクラシック音楽に興味を持つようになりました。 当時はサブスクリプションなんてありませんでしたし、なかなか親にCDを買ってもらうこともできませんでしたので、主にNHKのテレビ番組やラジオで、さまざまな演奏に触れていたのを覚えています。
その頃の僕は、バッハやべートーヴェン、ラヴェルなどといった作曲家ごとに音楽を聴くということよりも、画面に映し出されたりラジオのパーソナリティから紹介される指揮者や演奏家の魅力を探ることに興味があったように思います。
カラヤン、フルトヴェングラー、カルロス・クライバー、バーンスタイン、リヒテル、ポリーニ、アルゲリッチ、グレン・グールド、シフ…
この頃に出会った音楽家たちは、今でも変わらず好きです。
スタニスラフ・ブーニンも、その中の一人でした。ブーニンは、1985年のショパン国際ピアノコンクールを19歳の若さで優勝した、ロシア出身のピアニストです。
テレビ番組でたまたまブーニンが特集され、そこで初めてブーニンの演奏を聴いたときのことは、今でもはっきりと覚えています。 それはショパンコンクールでの演奏、「英雄ポロネーズ」でした。
▼ショパン:ポロネーズ第6番(英雄ポロネーズ) 変イ長調 Op.53(演奏:スタニスラフ・ブーニン)
ピアノから光が放たれているような、きらきらとした音。 なめらかでありながら、非常に粒立ちがよく、はっきりと聞こえる一音一音。くっきりとしていてメリハリのついたメロディの輪郭。
なぜか、ピアニストでありながら、デヴィッド・ボウイのようなロックスターの雰囲気と似たものを感じて、テレビに釘付けになってしまいました。技術がどうこう、解釈がどうこう、そんなことは何もわかっていなかったけれど、ただただ「これはとんでもなく格好いいものだ」と感じました。
当時、ピアノの練習が嫌で嫌で仕方なかった僕が、「ピアノってすごい」と思えたのは、間違いなくブーニンの存在があったからです。 結果的に、中学3年生までピアノを続けることができました。
「聴く」という営みの変容
その後、中学校では吹奏楽部でパーカッションを、高校では軽音楽部でドラムを担当し、ジャンルを横断しながら音楽を続けました。 そして芸術大学の音楽学科に進学し、4年間、西洋音楽を中心に学びました。 クラシック音楽だけでなく、民俗音楽、電子音楽、ジャズ、ロックやポップスまで。音楽を、構造や歴史、文化として捉える視点を身につけた時間でした。
そこから紆余曲折を経て、看護師の資格を取得し、現在に至ります。
精神科の看護師として働くようになってから、音楽の聴き方は大きく変わりました。
大学生の頃は、音楽を学べば学ぶほど、音楽以外の要素を含めて評価することに対して「それはどうなんだろう」という迷いがありました。けれど看護師となった今は、音楽を、音としてだけで聴くことができなくなりました。つまり、音楽の背景にある時間や物語を、どうしても重ねて聴いてしまうようになったのです。この傾向は、看護師としての経験を積むほど強くなっていったように思います。そうせざるを得なくなった、と言ったほうがいいかもしれません。
▼ショパン:12のエチュード Op.10「革命」(演奏:スタニスラフ・ブーニン)
失われたものと、残されたもの
先月、2026年1月。 10数年ぶりにブーニンのコンサートを聴きに行きました。 きっかけは、たまたま目にしたテレビのドキュメンタリー番組でした。
ここ10年ほど、ブーニンは左肩の石灰沈着性腱板炎による左腕の麻痺により、演奏活動を休止していました。 さらに、復帰が見え始めた2018年には転倒により左足を骨折。 骨折部位を固定するも、アレルギー反応が出て炎症を起こし、さらに持病のⅠ型糖尿病の影響で免疫機能が低下。 血流障害から壊死を起こし、左足首を約8センチ切除して縫合する大手術が行われました。
ピアニストにとって、足は手・指と同じくらい大切です。 ピアノには3つのペダルがあり、ペダルを両足で操作することで、音の響きを支えているからです。 医師からは、左足の切断を提案されたようですが、ブーニンはそれを固く拒否し、足を短くするという選択をしました。番組の中で、ステージへの復帰を目指すブーニンはこう語っていました。
「技術的に完璧でなくてもいい。 人に感動を与えられる美しい演奏がしたい。」
それでも美しかった
コンサートは、正直、全盛期のような演奏ではありませんでした。
テンポは不安定で、決して派手で強い音ではなく、たびたびミスタッチもあり、指の動きに不安を感じる場面もありました。 SNSには、厳しい感想も並んでいました。そこで見たすべての意見に対して、僕は「それもそうだな」と思いました。
それでも、ブーニンの演奏は、確かに美しかった。どれだけ技術的な全盛期から離れていても、確かにそこには「ブーニンにしか出せない音」がありました。 初めて彼の演奏を聴いたときと、同じ響き。 バッハの《主よ、人の望みの喜びよ》では、一瞬の沈黙のあと優しく奏でられた冒頭のあのメロディに、自然と涙が出ました。
あれほどの英才教育を受け、圧倒的な技術を持っていて、大観衆を沸かせてきたピアニストが、自分の演奏に対して「技術的に完璧でなくてもいい」と語るまでに至る過程。 そこにあったであろう苦悩や葛藤を思うと、とてつもなく胸が詰まります。 失われたものではなく、残っているものに、彼は人生を賭けたのだと思います。
思うように動かない左手。特注の厚底靴と杖。 それでも、あるがままの姿で、しかもたった一人でステージに立ち、不完全な状態でも音を鳴らすという選択。どれだけ覚悟のいることだろうか。そこには、音楽に対するブーニンなりの倫理があったのだと思います。
▼シューマン:色とりどりの小品 Op.99、ショパン:マズルカ Op.67-4(演奏:スタニスラフ・ブーニン)
残されているものを探す
僕は看護師です。 看護の現場では、元通りにならない状況に、何度も立ち会います。 病気や障害、老い。 できていたことが、できなくなる。 完全な回復が望めない場面も、少なくありません。
そして、その度に、何が残されているのかを探すことになります。その人が「自分らしくいられる状態」を一緒に探し続けることが僕の仕事だと考えています。 そのためには、人をある一点で評価するのではなく、揺らぎや変化を含んだ存在として見つめる視点が必要だと考えています。これは、クライシス・プランの研修などで、いつも話すことです。
ブーニンの演奏を、演奏という結果だけで見れば「不完全なもの」と評価されてしまうのかもしれません。 けれど、その背景や時間、その人が歩んできた過程まで含めて見たとき、あのステージは、まったく違う意味を持ち始めます。
音楽を専門的に学んできた人の中には、そうした聴き方に異論を唱える人もいるでしょう。そういう音楽との向き合い方があってもいいし、違ってもいいと思っています。 僕は「音楽を専門的に学んだ看護師」だから、僕の聴き方には、僕自身の背景があるのです。
もう一つの問い
失われたものではなく、今ここにあるものに目を向けること。 ブーニンの演奏を聴きながら、 音楽も、看護も、同じ問いのそばに立っているのだと感じました。
また、あの夜の演奏は、僕にもう一つの問いを残しました。「あなた自身はいま何を持っているか見ていますか?」と。
僕たち看護師もまた、完璧ではありません。揺れながら、迷いながら、それでも現場に立ち続けているのです。だからこそ、今ここにある力や想いを、自分自身にも向けたいと思うのです。
大阪市、寝屋川市、守口市、
門真市、大東市、枚方市全域対象
“精神科に特化”した
訪問看護ステーション
「くるみ」
平日・土曜・祝日 9:00〜18:00
【日曜・お盆・年末年始休み】
※訪問は20時まで
対応させていただいております。
※補足
2026年2月20日、ブーニンの映画が公開されるようです。ブーニンその人だけでなく、ブーニンの周りの人たちがブーニンを復帰までどう支えたのか、という映画でもあると思います。看護の視点で僕は観たいと思っています。